その他
2025.11.25
2025.7.2
2025.7.14
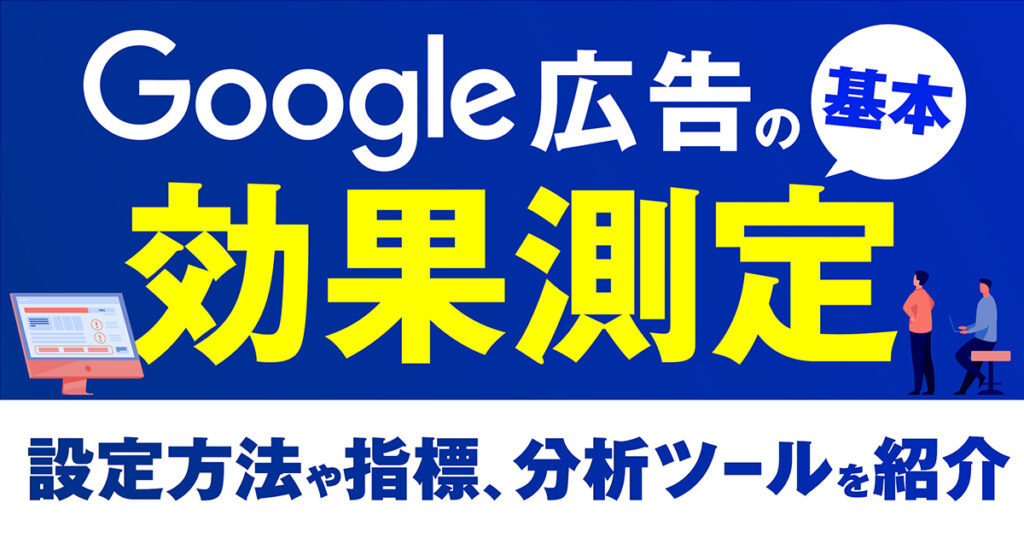
サービスを詳しく知りたい方はこちら
「Google広告の効果測定をしたいけれど、やり方が分からない」
「どの指標を重視すべきか迷ってしまう」
「Google広告の効果測定で成果を上げるにはどうすればいいの?」
上記のような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、Google広告の効果測定の設定方法や見るべき指標、分析ツールを紹介します。
効果的な広告運用をするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
Google広告キャンペーンで成果を上げるには、定期的な効果測定が欠かせません。
常に広告の状況を把握していればタイムリーな最適化が可能となり、結果として広告の成功率を高められるからです。
一方で効果測定によるデータ分析を怠ると、広告キャンペーンがうまくいかなかったり、貴重な広告費を無駄にしてしまう可能性があります。
そのため、効果測定を行って分析・改善を繰り返し、広告運用の成果を最大化していくことが重要です。
Google広告には、インプレッションやCTR、CPC、CV、CVRなど広告効果を測定するための主要な12指標が用意されています。
これらの指標により、広告のリーチ状況やユーザーの反応度、費用対効果、成果達成状況を把握できます。
さらに、広告費あたりの売上を示すROASや利益を示すROI、顧客生涯価値を表すLTV、そしてビジネス目標の達成度合いを測るKGI・KPIといった指標も含まれ、広告の効果を多角的に評価することが可能です。
以下では、それぞれの指標の意味と重要性を解説します。
インプレッションとは、広告がユーザーに表示された回数を表す指標です。
インプレッション数を把握すれば、広告がどの程度多くのユーザーにリーチしたかを知ることができ、インプレッションが増えるほど一般的にブランドの認知度向上につながります。
CPM(Cost Per Mille)は広告の表示1,000回あたりの費用を示す指標です。
インプレッションの費用対効果を把握するために用いられ、ブランド認知向上など広告の露出を重視する場合に特に注目すべき指標といえます。
例えば、CPMは「広告費用 ÷ インプレッション数 × 1,000」の計算式で算出され、CPMが低いほど少ない費用で多くのユーザーにリーチできていることになり、費用効率の良い広告配信ができていることを意味します。
CTR(Click Through Rate)は広告の表示回数に対してユーザーがクリックした割合を示す指標です。
CTRが高いほど配信した広告の内容(テキストや画像など)がユーザーに響いていることを意味し、より多くのユーザーをサイトに誘導できるため最終的なコンバージョンにも良い影響を与えやすくなります。
一方で、CTRが低い場合は広告の訴求力に課題がある可能性があり、広告プラットフォーム上の評価も下がって競合との入札競争に勝ちにくくなるなど、広告効果に悪影響を及ぼす恐れがあります。
そのため、CTRを向上させることはクリック単価の抑制や掲載順位の維持にもつながり、広告効果改善の重要ポイントとなります。
CPC(Cost Per Click)は広告が1回クリックされるごとに発生する費用を表す指標です。
CPCをモニタリングすることで、広告に対する費用対効果を測定できます。
もしCPCが高騰しているのにコンバージョンにつながっていない場合、それは競合が強く入札競争に勝ちにくい状態である可能性があります。
そのような場合、キーワードの変更などでCPCを抑えつつ広告の掲載順位を維持する対策が有効です。
適切なCPC管理によって、必要以上の広告費をかけずに効率良くユーザーを獲得することができます。
CV(コンバージョン)とは、広告を経由したユーザーが設定された目的(例:商品の購入や問い合わせ)を達成した回数を表す指標です。
CVはビジネスの売上や利益に直結する重要な指標であり、マーケティング施策の中でも特に重視すべき数値です。
例えば、CVが伸び悩んでいる場合、その原因は広告だけでなく広告から誘導された先のWebページに問題があるケースもあります。
そのため、広告のCVが低いときはサイトの内容や導線も含めて俯瞰的に見直し、ボトルネックを特定する必要があります。
CVR(コンバージョンレート)は広告をクリックしてサイトを訪問したユーザーのうち、どの程度がコンバージョンに至ったかを示す割合です。
CVRもCVと同様に売上や利益に直結するため、高いに越したことはありません。
もしCVRが低い場合、広告の内容と訪問先ページの両面から原因を分析する必要があります。
広告では適切なユーザーを集客できているか、また訪問先のページでユーザーが離脱する要因はないかなどを精査し、課題を特定しましょう。
CVRを改善することは、限られたクリックを無駄にせず成果に結びつける上で重要です。
CPA(Cost Per Action)は1件のコンバージョンを獲得するために必要な広告費用を示す指標です。
広告の費用対効果を計測する上で欠かせない指標であり、広告運用を開始する際にはまず目標とするCPAや許容できる最大CPA(限界CPA)を設定しておくことが重要です。
例えば「1件のコンバージョン獲得に○円までなら費用をかけられる」という基準を事前に決めておけば、出稿後に想定以上の赤字が出る事態を避けることができます。
また、広告配信後は実際のCPAが目標値に対してどうだったか必ず確認し、費用対効果の結果をレポートにまとめて次の施策に活かしましょう。
ROAS(Return On Advertising Spend)は広告費に対する売上高の比率を示す指標です。ROASの値が高いほど、使った広告費に対して大きな売上を獲得できていることを意味します。
例えば、100万円の広告費で200万円の売上が上がった場合、ROASは200%になります。
ROASが高いということは広告の投資対効果が高い状態と言えますが、ROASの数字だけで安心せず、その成果を生んだ広告戦略が適切だったか分析しておくことも必要です。
また、ROASはあくまで「売上」の指標であり最終的な利益までは考慮していないため、広告の効果測定では利益指標であるROIも併せて確認することが重要です。
ROI(Return on Investment)は広告費用に対する最終的な利益の割合を示す指標です。
ROASが広告費に対する売上であったのに対し、ROIは投資したコスト全体に対して得られた利益がどれくらいあるかを測る指標となります。
例えば、100万円の広告費で最終的に300万円の利益が生まれた場合、ROIは300%になります。
ROIが100%を超えていれば広告投資によって利益が出ている状態と判断できます。
ただしROIの計算方法はビジネスの状況によって異なる場合もあるため、自社の状況に合わせた算出が必要です。
またROIを向上させるには、より費用対効果の高い広告戦略の立案と実行が重要で、常に利益ベースで広告の成果を評価・改善していく姿勢が求められます。
LTV(Life Time Value)とは、1人の顧客が生涯にわたって自社の商品やサービスに支払う合計金額を表す指標です。
LTVが高い顧客ほど生涯を通じてもたらす売上が大きく、獲得する価値が高いと言えます。
例えば、単価10,000円の商品A(利益率30%)をある顧客が月1回購入し、それを3年間継続した場合、その顧客のLTVは「10,000円 × 利益率30% × 12ヶ月 × 3年=108,000円」と算出できます。
この計算結果から、ひとりの顧客を獲得するためにかけられるコストは108,000円以内に抑えるべきだという判断も可能です。
LTVを把握することで、顧客獲得にかける予算配分やマーケティング戦略の改善に役立ち、長期的な利益最大化につなげることができます。
KGI(Key Goal Indicator)はビジネス目標として設定された指標の中で、最終的な目的(ゴール)を示すものです。
たとえば「年間売上○○円達成」や「営業利益△△円確保」といった経営上の最終目標がKGIにあたります。
KGIを明確に設定することで、広告戦略やマーケティング施策の方向性をブレずに定めることができ、日々の施策もこの最終目標に向けて迷いなく進めることが可能になります。
KGIは広告効果測定の最上位に位置づけられる指標であり、ビジネス全体の成功指標と言い換えることもできます。
KPI(Key Performance Indicator)は、KGIという最終目標に対して現在どの程度達成できているかを測るための指標です。
KPIは中間目標とも言え、KGIを達成するために設定された具体的な数値目標を指します。
最終目標が売上○○円であれば、そこに至る途中経過として「コンバージョン件数」「コンバージョン率」「サイト訪問数」や「獲得リード数」などをKPIとして定め、それぞれに目標値を置きます。
こうしたKPIを定期的に追跡することで、KGIに向けた進捗を定量的に評価でき、必要に応じて戦略の修正や施策の強化を行うことができます。
KPIはKGI達成への道標となる指標と言えます。
Google広告の効果を正しく測定するには、大きく2つの方法があります。
1つ目はGoogle広告のコンバージョン計測機能を使って、広告経由のコンバージョンを追跡する方法、2つ目はGoogle広告アカウントをGoogleアナリティクスと連携してサイト全体のデータと紐付けて分析する方法です。
それぞれの手法を活用することで、広告の貢献度を詳細に把握し、より精度の高い効果分析が可能になります。
まず、Google広告側でコンバージョン計測の設定を行い、広告経由の成果を記録できるようにしましょう。
Google広告の管理画面で、購入完了や問い合わせ完了など計測したい各イベントごとにコンバージョンアクションを作成します。
設定手順としては、管理画面左上の「目標」メニューからコンバージョンの項目に移動し、「+新しいコンバージョンアクション」を選択して必要な情報を入力します。
この設定により、広告をクリックしたユーザーが購入や問い合わせなど価値のある行動を完了したかどうかをGoogle広告で追跡できるようになります。
効果測定したいコンバージョンを追跡するため、最初にGoogle広告の管理画面でコンバージョンアクションを新規作成します。
Google広告の管理画面上部にある「目標」をクリックし、コンバージョンの設定画面へ移動します。
そして「コンバージョンの概要」から「+新しいコンバージョンアクション」を選択し、計測したい種類(例:ウェブサイト、アプリ、電話など)を選んで必要項目を設定します。
例えば「購入完了」を計測したい場合は、コンバージョン名や価値、カウント方法(1回あたりか複数回か)などを入力し保存します。
これでGoogle広告側に追跡したいコンバージョンの枠組みが作成されました。
次に、先ほど作成したコンバージョンを計測するタグを自社ウェブサイトに設置します。
Google広告の管理画面から取得できるコンバージョンタグを、計測対象のページのHTMLソース内に埋め込んで設定していきます。
一般的には、コンバージョン完了ページ(例えば「お問い合わせ完了」や「購入ありがとうございました」ページ)の`<head>`タグ内に、Googleタグ(旧グローバルサイトタグ)およびコンバージョンのイベントスニペットを貼り付けます。
例えば、Googleタグマネージャーを利用している場合は、新しいタグとして「Google広告のコンバージョントラッキング」を選択し、先ほど取得したコンバージョンID等を入力して配信する設定を行います。
適切にタグを設置すれば、ユーザーが広告経由でサイト内の目標ページに到達した際にその情報がGoogle広告側に送信され、コンバージョンとして計上されます。
もう一つの効果測定方法は、Google広告アカウントとGoogleアナリティクスを連携することです。
広告とサイト分析ツールを連携させることで、お互いのデータを相互に活用した高度な分析が可能になります。
設定手順としては、Google広告の管理画面で「ツールと設定」→「リンクアカウント」を開き、一覧から「Googleアナリティクス(GA4)」を選択して該当のGA4プロパティとリンクします。
あるいはGoogleアナリティクス側の管理画面から「Google広告リンク」を設定してリンクすることも可能です。
連携が完了すると、Googleアナリティクス上でGoogle広告のクリック数や直帰率などのデータを確認でき、またGoogle広告の管理画面でGoogleアナリティクス由来の指標(セッション数、滞在時間、直帰率など)をインポートして分析することもできます。
このようにデータを統合することで、広告の効果測定精度が向上し、より的確な最適化施策(例えばサイト行動データを活用した広告調整やターゲティング強化)を打つことができます。
Google広告の効果測定を行う際にGoogleアナリティクスと連携することで、得られるメリットがいくつかあります。
ここではデータの共有活用による分析精度向上、スマート自動入札の強化、そして高度なリマーケティングの実現という3つの主なメリットについて解説します。
Google広告とGoogleアナリティクスを連携すると、両プラットフォーム間で情報が共有され、一元的な分析が可能になります。
具体的には、Googleアナリティクス上で広告のクリック数やクリック単価、ユーザー数、直帰率、セッション数といったキャンペーンやキーワードに関する詳細データを閲覧できるようになります。
さらに、Google広告の管理画面側でもアナリティクスの指標(直帰率や平均セッション時間など)をインポートして表示できるため、広告経由のトラフィックの質を広告管理画面上で直接評価することが可能です。
このように情報を共有することで、広告クリック後のサイト上での行動や品質まで含めて統合的に分析でき、効果測定の精度が高まります。
Google広告のスマート自動入札も、Googleアナリティクスのデータ連携によって精度向上が期待できます。
スマート自動入札はユーザーのコンバージョン獲得に繋がるクリックを最大化するよう入札を調整してくれる機能ですが、アナリティクスと連携することでサイト上でのユーザー行動データなど追加のシグナルを考慮した最適化が可能になります。
例えば、アナリティクスのデータを取り込むことで「コンバージョンに至りにくいクリック」を機械学習が判断し、無駄なクリックや不要なコストを自動的に抑制してくれます。
その結果、同じ予算でもよりコンバージョン見込みの高いクリックに絞って配信されるため、コンバージョン数増加やCPA改善に繋がります。
このように、データ連携によってスマート入札の判断材料が充実し、広告運用の効率と効果が一段と向上します。
Google広告とアナリティクスの連携により、より高度なリマーケティング施策も可能となります。
リマーケティングとは一度サイトを訪れたユーザーに対し再度広告を配信する手法ですが、アナリティクスを活用することでサイト上でのユーザー行動に基づいた精緻なリマーケティングリストを作成できます。
例えば、直帰率が低く長時間サイト内に滞在したユーザーや、複数回購入実績のあるユーザーなどをアナリティクス上でセグメント化し、そのリストをGoogle広告にインポートして狙い撃ちで広告を配信することができます。
こうしたアナリティクス由来の条件に基づくリマーケティングにより、単に広告を一度見ただけのユーザーに比べ、購買意欲の高いユーザーへ集中的にアプローチでき、コンバージョン率向上が期待できます。
連携によるリマーケティング強化で、広告予算をより効率的に使い成果につなげることが可能です。
効果測定を行うにあたり、知っておくべき注意点もあります。
Google広告の効果が現れるまでの一般的な期間や、アナリティクス連携時のアカウント権限の確認、さらにはGoogle広告とアナリティクス間でデータの定義やカウント方法が異なる点について、事前に理解しておきましょう。
Google広告の効果が十分に表れるまでには一定の時間がかかることに注意が必要です。
一般的な目安として、広告運用開始から成果が安定して出始めるまでに約3ヶ月~6ヶ月程度は要するとされています。
これは、運用開始直後の1ヶ月目は検索語句データなどの蓄積が少なく、十分な最適化の材料が揃っていないため成果が出にくい一方、数ヶ月かけてデータが蓄積されるほど改善のスピードが上がり広告配信の最適化が進むためです。
したがって、広告運用開始後すぐに結果が出なくても焦らず、最低でも数ヶ月スパンでPDCAサイクルを回しながら効果測定を続けることが重要です。
Google広告とGoogleアナリティクスを連携して効果測定を行う際は、両アカウントの権限設定にも注意しましょう。
連携には、Googleアナリティクス側でプロパティ編集の権限を持っていること、およびGoogle広告側でアカウント管理者の権限を持っていることの2点が必要条件です。
実際に連携設定を行う前に、Googleアナリティクスの管理画面で自分のユーザー権限が「編集」権限になっているか確認し、Google広告の「アクセス管理」画面で自身の役割が「管理者」となっているか確認してください。
必要な権限がない場合、データ連携やコンバージョン情報のインポートが正しく行えない可能性がありますので、事前に権限を整えておきましょう。
GoogleアナリティクスとGoogle広告ではトラッキングの仕組みや指標の定義が異なるため、両者の数値を比較する際には注意が必要です。
例えば、Googleアナリティクス側では広告のインプレッション数を確認することができません。
そのため、GA上ではCTRを直接算出することができず、主にクリック後のセッション数や行動指標を用いて分析することになります。
また、コンバージョンの計測方法にも違いがあります。
Googleアナリティクスではコンバージョンが発生した日時にコンバージョン数が計上されますが、Google広告では最後に広告をクリックした日時にコンバージョンが計上されます。
さらに、Googleアナリティクスでは1セッション中に1回しかコンバージョンがカウントされないのに対し、Google広告では1クリックから複数回のコンバージョンが発生した場合にそれぞれ計上する設定も可能です。
このように両者の計測ルールの違いから数値にズレが生じることがあるため、効果測定結果を解釈する際にはどの指標がどのように計測されているかを理解した上で判断するようにしましょう。
効果測定の結果を広告運用の成果向上につなげるためのポイントを紹介します。
定期的なレポートの作成・活用による現状把握と改善策の抽出、Googleタグマネージャーを用いたユーザー離脱ポイントの解析、そして主要指標の分析による具体的な改善箇所の特定といったアプローチが有効です。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
定期的に広告効果のレポートを確認・分析することは、広告運用の改善に欠かせません。
広告レポートを適切に活用することで、キャンペーン全体のパフォーマンスを多角的に評価し、効果的な改善策を見出すことができます。
例えば毎週や毎月の定期レポートを見れば、どの広告グループやキーワードが好調で、どの部分に課題があるかを客観的な数値で把握できます。
レポート分析で得られた気づきを基に入札単価の調整や予算配分の変更、クリエイティブの改善など具体的な施策を講じることで、次の期間のパフォーマンス向上につなげられます。
要するに、データに基づいて現状を正確に把握し、施策のPDCAを回す**ためにレポートの確認・分析が重要なのです。
Google広告の管理画面にはレポートをスケジュール配信する機能があり、決まった頻度で最新データのレポートをメール受信することもできます。
また、必要に応じてLooker Studio(旧データポータル)や広告レポート自動化ツールを活用すれば、複数媒体のデータを一元化したレポートを自動で生成することも可能です。
こうした自動化設定によりレポート作成の工数が削減され、担当者は分析と改善策立案により多くの時間を充てることができます。
レポートで明らかになった課題に対して、次のアクションを明確にしましょう。
例えば「コンバージョン率が低下しているキャンペーンAがある」とレポートで分かったら、キャンペーンAのランディングページ改善や入札戦略の見直しなど具体策を立案します。
また「費用対効果の悪いキーワードXが判明した」場合には、そのキーワードの入札単価を下げる、もしくは停止して予算を他に振り向けるなどの対応につなげます。
このように、レポート分析から得たインサイトを確実に運用改善プランに落とし込み、実行に移すことが重要です。
レポートを作成して終わりではなく、そこからPDCAサイクルを回していくことで、広告効果を継続的に向上させることができるでしょう。
Googleタグマネージャーを活用することで、ユーザーがサイト内でどこで離脱しているかを詳細に把握できます。
例えば、GTMでスクロールの深度を計測すると、ユーザーがページ内のどのコンテンツで離脱しているかを把握でき、ページ改善のための仮説立てに役立ちます。
たとえば長いランディングページであれば、GTMのトリガー設定によってページの50%や75%までスクロールしたかどうかをイベント計測し、多くのユーザーが50%地点で離脱していると分かればその付近のコンテンツに課題があると推測できます。
同様に、GTMでクリックイベントを計測することで、「カートに商品を入れたが購入手続きに進まない」といった離脱ポイントも洗い出せます。
こうして明確になった離脱ポイントに対して、該当箇所のUI改善や案内の強化など対策を講じることで、コンバージョン率の向上につなげることができます。
広告の主要指標であるCTRやCVRの値を分析することで、どこを改善すべきかが見えてきます。
広告のCTRとCVRの両方が振るわない場合、広告のターゲティングや訴求内容そのものに課題がある可能性が高いです。
この場合、想定するユーザー層へのアプローチやクリエイティブを一から見直し、適切なターゲット設定と魅力的な広告内容に改善する必要があります。
一方で広告はクリックされているがコンバージョンに繋がっていない場合、問題はクリック後の段階にあると考えられます。
具体的には、ランディングページの内容やユーザー導線に改善余地がないか確認します。
広告で約束した内容とランディングページの情報が食い違っていればユーザーは離脱しやすくなりますし、フォームの使い勝手が悪ければ途中離脱を招きます。
このようにCTRとCVRの組み合わせから「広告側の問題」か「サイト側の問題」かを切り分け、改善箇所を特定することで、効率的に広告効果を高めることができます。
Google広告の効果測定は、単に数値を追うだけでなく、その結果をもとに施策を改善し続けることまで含めて初めて成果につながります。
継続的に正しく効果測定を行い、分析と改善を繰り返すことで広告運用の成果を最大化できるのがWeb広告の強みです。
ぜひ本記事で紹介した指標や手法をマスターし、データに基づくPDCAを回していくことで、Google広告から得られる売上を着実に伸ばしていきましょう。
効果測定を味方につけて、より少ない広告費でより大きな成果を実現する広告運用を目指してください。
Writer GMSコンサルティング編集部 マーケティング部
私たちは現在の自分に甘んじず、チャレンジをすることで、お客様にプロとしての価値を提供いたします。常に知識・技術をアップデートし、お客様の成長に貢献してまいります。
広告運用でお困りの方はお気軽にお問い合わせください